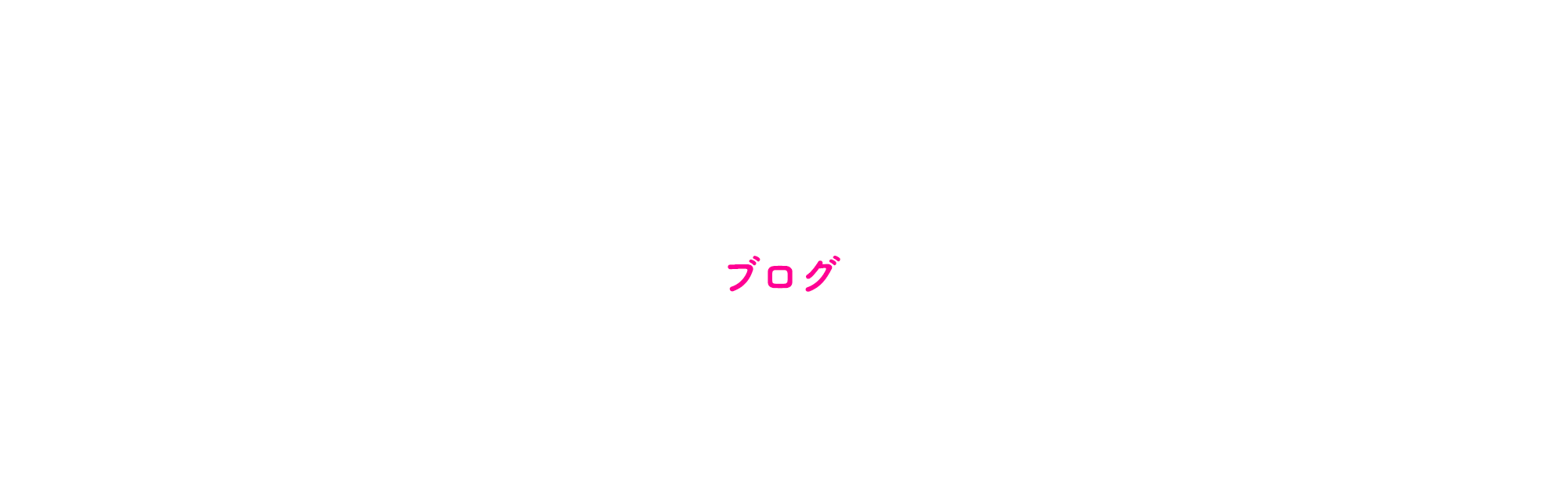今日の栗東は、朝からスカッとした青空の広がるいいお天気です。
昨日の日曜日、久しぶりに時間があったので、お洋服の入れ替えをしました。
夏のお洋服を片付けながら、「また、来年も着れるといいなぁ〜」と。。
来年も同じ洋服を着るためには、何とか!体型を維持しなくては!
そこが大きな問題になるお年頃…、冬の過ごし方が大きなポイントです〜(u_u)。
そうそう!前回のブログでご紹介したい本がもう一冊ありました。
レッスンの際に、よく生徒さん達に見ていただくピアノの絵本。
☆ カワイ出版さんの『楽器の絵本 ピアノ 』です。
大好きな青島広志先生の講座に参加した際に、紹介していただいた絵本です。
「ピアノの先生が、まずはしっかりとピアノのことがわからないといけませんよ。」と、
お話になって、「もしかして、わかってないかも…。」と購入した絵本です。
この絵本は、今現在のピアノのお話を中心に進められています。
『だんめんず』と同じく、ピアノの断面図を2ページを使って描いています。
どうやってピアノの音が出るのかを、丁寧に説明してくれている絵本です。
何度聴いても、なかなかわかったようでわからないピアノの仕組みですが、
生徒さんと一緒に読んだり眺めたりするうちに、理解したように思います。
レッスンをしていて、よく生徒さんに聞かれることがあります。
「せんせー、真ん中のペダルって、いつ使うの?どんな時に使うの?」
「ぼくんちのピアノの真ん中のペダルは、押したら音が小さくなるけど、
せんせーのピアノはならないね。なんでかなぁ〜、壊れてたりする…?」と。
グランドピアノの右、左のペダルは、踏んで見ると変化がわかるのですが、
そう!真ん中のペダルって、ただ踏んだだけではなかなか変化がわからないですよね。
この絵本の中では、この真ん中のペダルのお話も書かれています。
『ソステヌートペダル』という名前のペダルです。
私は、このペダルのお話をする時に、こんなことをよくしてみせます。
まずは、真ん中の『ドミソ』の3つの鍵盤を音を出さないようにして下まで押さえます。
そして、真ん中のペダルを踏みます。
そして、ペダルを踏んだまま、いろんな鍵盤の音を弾きます(低い音が効果的)。
そうすると!あらあら不思議!音を出して弾いた音はすぐに消えるのに、
最初に音を出さずに弾いた『ドミソ』の音が、ナント❗️綺麗に聴こえます。
ウフフフ…この時の生徒さんたちのお顔は、それはそれは!いいお顔になります〜(≧∀≦)。
絵本を通して、『ピアノ』という楽器の魅力が、少しでも伝わったなら、
きっと、ピアノを弾くことが、もっともっと好きになれる気がします。
そういえば…先日の斎藤守也さんのレクチャーコンサートの際にも、
「ピアノが上手くなるためには、ピアノという楽器を知って好きになること」
そう、お話されてましたっけね。。